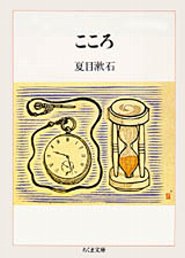「お国」はどちら?
『こころ』の舞台は明治時代末期。語り手である「私」が出会った「先生」が背負う昏い秘密をめぐる物語だ。維新と呼ばれた革命の時代の終焉とともに、主人公2人の運命も強く揺さぶられていく。
明治。それは私たちの先祖が〝日本人〟を自覚したであろう時代。日本語のあり方についても実験と議論がなされ、近代日本文学が産声を上げた時代でもあった。
作中、鳥取生まれの父と東京の母を持つという「先生」の奥さんが、自らを指して『本当いうと合の子なんですよ』と言うシーンがある。この時代、「国はどこ?」と問われれば、それは十中八九、日本国内の郷里を意味しただろう。ほとんど地ならしされたように、各地の文化や特色が希薄になった令和の現代では、たまたま鳥取に生まれたことは、さほど特筆すべき個性にはならない。しかし、江戸期の幕藩体制と熾烈な内戦がつい数十年前に終わったばかりの当時、それは個人を示す重大な〝属性〟だったに違いない。現代人が「日本」という一語に託してシンプルなひとまとまりだと思い込んでいるこの国は、わずか100年ちょっと前まで、もっと複雑に多様な歴史と風俗が絡み合った、混沌とした集合体だったのだ。
今春、国内最後の明治生まれの男性が亡くなったというニュースが流れた。明治は遠くになりにけり。しかし百年たとうが千年たとうが変わらないものはある。普遍的な人間の「こころ」を足掛かりに、作中の時代感覚を想像することは、読書の大きな醍醐味のひとつだ。